コレもそうなの?!自然をヒントに生まれたアイデア特集 PR含む

素晴らしいアイデアというのは、ふっと浮かんでくるようで、実は何かをヒントにしていることが多いものです。
過去の体験や知識、普段よく目にするものなど、小さなタネがアイデアのもとになっています。
その中でも、自然はアイデアの宝庫です。
私たちの生活や身近なところには、自然をヒントにしたテクノロジーが数多く存在します。
そこで今回は、自然をヒントに生まれたアイデアをご紹介します!
生き物の動きや特性を利用したテクノロジーは、家電や医療器具にも使われていますよ。
自然をヒントに生まれたテクノロジーは、生体模倣(バイオミメティクス)と呼ばれる

生き物の動きなどを観察・分析して生まれたモノづくりの科学技術は、生体模倣(バイオミメティクス)と呼ばれます。
トンボの180度展開する超広角の眼や、ホタルの発光パターンにおける1/fのゆらぎなど、人間にはない植物や生物が持つ優れた能力は、さまざまなモノづくりのヒントとなっているのです。
そのため実は知らないだけで、普段あなたが使っているものも自然をヒントに生まれた製品かもしれませんよ。
アイデアのヒントになった、生き物の特性まとめ
自然をヒントに生まれたテクノロジーは数多くあり、私たちの暮らしの至るところで活用されています。
応用されている分野は、日常生活からビジネスまで多岐に渡るので、中には「えっ、これってそうなの?」と思うようなアイデアもあるかもしれません。
ぜひチェックしてみてください。
ハニカム構造(ハチの巣)

正六角形を並べた形しているハニカム構造は、英語で「ハチの巣」という意味です。
ハニカム構造は軽量で、強度が高く、衝撃吸収性に優れるという特徴があるため、昔から航空機の素材に利用されています。
他に、ハニカム構造の軽さと強度を生かした素材としては、ペーパーハニカムがあります。
ペーパーハニカムとは、環境に優しいエコな紙素材のことで、ダンボールや発砲スチロールの代わりに利用されています。
また、断熱や防音効果もあるので、ドアやパーテーションなど建材用芯材にも採用されている素材です。
蚊の針

蚊からヒントを得て誕生したのが、痛くない注射針です。
超極細でつくられた針は、蚊の針のギザギザした形をマネて作られています。
こう聞くと一見痛そうに感じますが、実際は皮膚に刺すときの痛みを軽減してくれます。
単に針が細いだけでは折れる心配もありますが、そこは工場のプレス加工の技術を利用することで、細くても折れない針を完成させました。
昔の注射にあった「痛い」「怖い」といったイメージを払拭させた発明品は、「こわくない注射針」として知られています。
ゴボウの実

ゴボウの実をヒントにして生まれたのが、ベルクロ(マジックテープ)です。
ベルクロはバッグや靴など幅広いシーンで利用されている、ペタッと付けてバリッと剥がす面ファスナーです。
おそらく、一度は使ったことがあるのではないでしょうか?
ゴボウの実は先端がフック状の形をしていて服などにくっつくので、オナモミと同じく「ひっつき虫」と呼ばれます。
着脱が簡単な面ファスナーは、もう私たちの生活に欠かせないですね。
ちなみにマジックテープという名称は、株式会社クラレの登録商標です。
ハチドリのホバリング能力

ハチドリの能力は、ドローンのホバリングに応用されています。
ホバリングとは空中で停止している状態のことで、ヘリコプターがその代表ですね。
ハチドリは鳥類では珍しく、長時間空中で静止していられる鳥です。
風が吹いても同じ場所に止まっている能力、静止に加えて後退する動作などもテクノロジーに生かされているとされます。
ハスの葉

ハスの葉の特性を応用して生まれたのが、撥水性のあるウェアやヨーグルトのフタです。
ハスの葉の表面は、水を弾き、汚れにくい構造になっています。
レインウェアや靴、バッグなど撥水性を持った製品は、ハスの葉の構造をヒントに作られたんですね。
ヨーグルトのフタに撥水性がなかったら、おそらくもっと中身がフタにくっついていたでしょう。
サメ肌

サメの表皮構造は、競泳水着に応用されています。
スピードを重視する競泳で水着に求められるのは、高いフィット感です。
サメは、凸凹の肌表面で水中で抵抗を減らし、水流をコントロールしています。
体の部位によってうろこの密度が違うといった特徴も、テクノロジーに利用されています。
スポーツブランド<Speedo>は、サメ肌をモチーフにした水着を開発したことで有名です。
カワセミのくちばし

新幹線の先端部分は、カワセミのくちばし構造をヒントにしています。

以前まで時速300km近くで走る新幹線は、高速でトンネルに侵入すると大きな音を発生させていました。
トンネルドンとも言われる現象は、新幹線がトンネル内の空気を圧縮して、空気砲のように出口へ押し出そうとするために起こります(トンネル微気圧波)。
この現象は、近隣の騒音や振動にも影響するので、鉄道の技術開発関係者は、長年このトンネル微気圧波に悩まされていました。
それを解決したのが、カワセミのくちばしです。
カワセミのくちばしは、水面の小魚をスムーズに捕らえるため、細く尖っています。
新幹線の先端にカワセミのくちばし構造を応用することで、空気抵抗は減少し、騒音も緩和されました。
フクロウの羽

また、新幹線のパンタグラフは、フクロウの羽をヒントにしています。
パンタグラフとは、新幹線の外に付いている突起状のもので、走行中に空気抵抗を受けるため騒音の原因となりやすい部位です。
そこで、技術開発者はフクロウの羽に目をつけました。
フクロウの羽は、他の鳥にはないギザギザした構造をしているため、音もなく静かに飛ぶことができます。
獲物に気づかれないための生存戦略と言えますが、パンタグラフにフクロウの羽構造を応用したことで、以前より騒音が30%カットされています。
かたつむりの殻
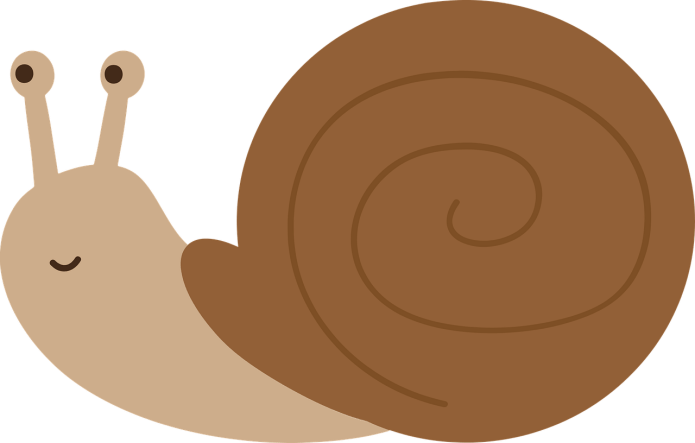
かたつむりの殻をヒントにしているのは、家の外壁タイルです。
かたつむりは汚れやすい自然の中で暮らしているのにもかかわらず、いつも殻はキレイな状態を保っています。
不動産メーカーや建材製品を扱う業界では、このかたつむりの殻が持つ防汚効果に注目しています。
外壁の美観を長く保ち、メンテナンスも簡単にするには、かたつむりの殻が良いヒントになったんですね。
クモの糸

クモの糸の特性を利用した素材があるのを知っていますか?
人工のクモの糸繊維である「QMONOS(クモノス)」は、鋼鉄よりも強度があり、ナイロンよりも伸縮性に優れた次世代素材です。
原料に石油を使わないため、環境負荷の少ないサスティナブルな素材とも言われています。
2019年にはアウトドアブランド<THE NORTH FACE>から、このクモ糸素材を使用した「Moon Parka(ムーンパーカ)」が限定発売されました。
少し前までクモの糸による合成繊維は「夢の繊維」と呼ばれるほど、実用化は困難とされていましたが、テクノロジーは日々進化しているんですね。
イルカの尻尾と表皮のしわ

イルカの尻尾と表皮のしわは、<シャープ>の縦型洗濯機におけるパルセーターに応用されています。
パルセーターとは、洗濯機の底にあるプロペラみたいな部位です。
洗濯の際に水流を生み出す部位なので、重要なパーツと言えますね。
<シャープ>の縦型洗濯機は、イルカの尻尾の形や上下に蹴り出すリズム(ドルフィンキックパターン)をパルセーターに応用することで、水流を強化し、もみ洗いを効率的にしています。
また、表皮のしわをヒントにしたことで水中抵抗が減り、洗浄力も高まっています。
<シャープ>のネイチャーテクノロジーがすごい!

自然をヒントに数多くの製品を生み出している有名企業といえば、上記のイルカでもご紹介した<シャープ>です。
<シャープ>は自然の摂理から学び、暮らしにも環境にも優しいモノづくりをしています。
『ネイチャーテクノロジー』という言葉は<シャープ>の登録商標であり、2008年から研究開発を始め、これまで24品目の製品にネイチャーテクノロジーの技術を搭載してきました(2025年4月時点)。
先ほどのイルカの尻尾を応用した洗濯機もそうですが、他にも
- トンボの羽を応用にしたエアコン室内ファン
- アマツバメの高速飛行を応用したドライヤー
などを開発しています。
家電を買うときは値段やデザインに目がいきがちですが、こういった企業の製品開発ストーリーも購入を決めるきっかけになりますよね。
あわせて読みたい >> <シャープ>のネイチャーテクノロジーに学ぶ!アイデアの出し方
ポケモンも自然遊びから生まれた

今や知らない人がいない世界的大ヒット作『ポケットモンスター』も、自然をヒントに生まれた作品といえます。
ポケモン生みの親・田尻智氏は、子どもの頃、昆虫採集が好きでした。
その後、インベーダーゲームにハマり、ゲーム作りの道を歩むわけですが、1996年に発売されたポケットモンスター赤・緑には、田尻氏の少年時代の経験が色濃く反映されています。
- 「調べる・育てる・捕まえる」などクワガタ獲りでの経験
- 昆虫採集で感じたワクワク感
- 友達との交流
子どもから大人までの心をくすぐる冒険シナリオは、この自然遊びの経験がベースとなって生まれたわけです。
もし、外遊びの経験がある場合には、自身が「やっていて楽しかったこと」「おもしろかったこと」「驚いたこと」などが創作のヒントになるかもしれません。
あわせて読みたい >> はじまりは子どもの頃の昆虫採集『ポケモンをつくった男 田尻智』
まとめ

私たちの身の回りは、自然をヒントにした製品やテクノロジーが溢れています。
エアコンや洗濯機など普段何気なく使っている製品も、もしかしたら自然界の特性からヒントを得て誕生したものかもしれません。
仕事や事業でアイデアが出ないときは、自然からヒントをもらってみてはいかがでしょうか?




